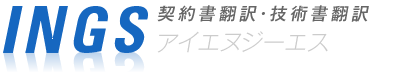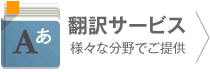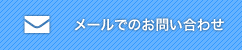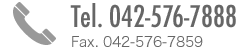以前、「「履行」、「~を履行する」の表現について」というブログを掲載したことがあります。その中で、「履行」、「履行する」、「履行される」の対象となる様々な要素があります。その中でも「債権」と「債務」は、契約書において「履行」密接にかかわっている言葉です。本記事では、契約書翻訳の実務経験を前提に、英文契約書の内容確認・リスクチェックの観点から解説します。
-債権・債務に関する英語表現のいくつか-
「債権」と「債務」とこれらにかかわる単語をいくつかあげてみました。
債権: a claim(claims); credit; receivables)
金銭債権:monetary claim)
貸付債権:loan claim)
不良債権:bad debt; a bad nonperforming loans; a bad credit
制限債権:claim subject to limitation
金銭債権:monetary claim
被担保債権:secured claim
債権者:creditor
債務:debt; liability; responsibility; *obligation
債務者:debtor;obligor
債務の責に帰すべき事由:case imputable to be accused of the obligor
債務の消滅:acquittance
債務整理:arrangement
債務超過:insolvency;liability exceeding assets
債務の引き受け:assumption of the obligation
-assignment of an obligationが「債権譲渡」とされる理由-
* 「obligation」を辞書(英和辞典)で調べてみると「obligation」には債務や義務といった意味のほかに「債権」、「債権(債務)関係」、契約(agreement)(法律用語)という意味も記載されています(債務の意味しか記載されていない辞書もあります。)これはclaimやreceivableなどが債権者の権利のみを表すのに対して「obligation」には、債権(権利)と債務(義務)の両方が含まれているからです。言いかえれば「obligation」は、債権と債務を含むその法的関係全体=を表す言葉です。英文契約書では債権譲渡はassignment of an obligation、債権法はthe law of obligationsとされています。これについては英米法と大陸法(日本法)との違いという点もありますが、ここでは触れません)。英文「the law of obligations」を債権法をとするのも、債権法が債権・債務関係を規律する法律である点から「obligation」が使われるのもうなずけます。英文契約書に「obligation」がつかわれている場合、文脈的に判断する必要がありますが、基本的には文脈上、債務、負債、義務等とする場合がほとんどであると思われます。
なを、債権譲渡:assignment of an obligationについては、日本語として考えた場合、文字通り債権をAからBに譲渡するといパターンを思い浮かべます。例えば、「債権の譲渡における債務者の抗弁(Defense of Obligor upon Assignment of Claim)」(民法)とか電子記録債権の譲渡(Assignment of Electronically Recorded Monetary Claims)(電子記録債権法)など、ここでは債権譲渡は「Assignment of Claim」とされています。したがってこの場合、債権譲渡契約は、Assignment Agreement of Claimsとしても問題ないと思います。
ただし、一旦日本語を離れて、英文契約書に「assignment of an obligation」と記載されていた場合、「obligation=債権債務関係全体」を表すため、文脈に応じた判断が求められます。
-creditの用法-
ここで、「Credit」についての英語独特の概念を思い出してみたいと思います。
例えばAがBに商品を販売し、その代金を後払いにした場合、Aは、Bに対する売掛金(債権)を有し、BはAに対する買掛金の支払い義務(債務)を負います。
この売買代金は、A(債権者)の立場では、「my credit to B」、一方、B(債務者)の立場では、「my credit from A」と表されます。このようにcreditは双方向で用いられることがあります。そのほか以下のような表現もあります。
A(債権者):
Accounts receivable from B
I have a receivable from B
I have extended credit to B(Bに信用を与えた)
B owes me(口語)
B(債務者):
Accounts payable to A
I have credit from A(Aに信用を与えられている)
I owe A(口語)
当社では、単なる翻訳という作業ではなく、最終的に使用される文書としての完成度を重視しています。契約書・専門文書の翻訳について、用途に応じた確認が必要な場合は、こちらからお問い合わせください。当社ではお客様の作成した翻訳文を原文と対比して校正するポストエディットも承っております。