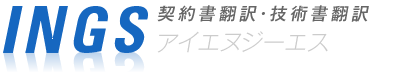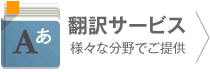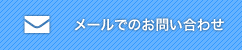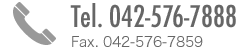今回は、天体の運行を通して、人名と固有名詞についての日本語と英語の読み方の違いを見てみます。
プトレマイオスの例-「タレミー」or 「プトレマイオス」
天体の運行に関する分野(例えば星術)では、多くの偉人・賢人の名前が出てきます。
その中に、「Ptolemy=プトレマイオス」の名前があります。
「Ptolemy」とは、*ウィキペディア(Wikipedia)によると、「クラウディオス・プトレマイオス(古代ギリシャ語: Κλαύδιος Πτολεμαῖος, ラテン語: Claudius Ptolemæus, 83年頃 – 168年頃)は、数学・天文学・占星学・音楽学・光学・地理学・地図製作学など幅広い分野にわたる業績を残した古代ローマの学者。英称はトレミー(Ptolemy)。エジプトのアレクサンドリアで活躍した。」となっています。
バイリンガルの人は、発音から来た名称そのまま「タレミー」と訳してしまいますが、日本語では「プトレマイオス」となります。
日本語のプトレマイオスは、ラテン語の「Ptolemæus」を一字一字読む「プ・ト・レ・マイ・オス」から来ています。では、英語の場合は、Claudius Ptolemyの「Ptolemy」を古代ギリシャの読み方の「ˈtɒləmi」と発音します。
発音的には、Wikipediaには「トレミー」となっていますが、「タレミー」の方がより近いと思います。実際には、「ト」と「タ」の間ぐらいの発音です。
翻訳物に「タレミー」と書いても、日本人には「タレミー」ではなじみがなく、一体誰のことは分かりません。反対に、外国人に「プトレマイオス」と言っても分からないので、Spellingを表示する必要があります。
ドイツの哲学者Emmanuel Kant(エマヌエルカント)(1724‐1804)が、1781年の著書、純粋理性批判(Critique of Pure Reason)の中でCopernican Revolution(コペルニクス革命)-Copernican turn(コペルニクス的転回)と名付けた地動説の提唱者のCopernicus(コペルニクス)の場合は、どのように発音するのでしょうか?発音は、「コウペルニカス」となります。
名前の読み方について「プトレマイオス」を例にとり、日本語と英語での違いを見ましたが、天体の運行についての話題にもどります。
地動説と天動説についての私見 -翻訳では言葉が反転-
Copernican theory(コペルニクス理論)におけるコペルニクス的転回とは、物事の見方が180度変わってしまう事を比喩した言葉です。あるいは、既物事を根本的に転換させた視点で考察する際の表現で、コペルニクスは、アリストテレスが提唱した天動説(geocentric theory)を捨てて地動説(heliocentric theory)を唱えたことに喩えています。コペルニクスが提唱した宇宙は、「中心火宇宙」であり、これは、「中心火」すなわち太陽を中心にした宇宙を考えたわけです。ここで初めて地球は、平面でなく、球体と考えられるようになりました。以前の考えを真っ向から反対し、全くの反対となったことが革命であり、急転回と言われる所以です。
天動説 vs 地動説
ちなみに、あくまでも私見ですが、天動説は「geocentric theory」ですが、「geocentric」は「地球を中心とした」の意味で、直訳的には「地球中心説」となるようです。反対に、地動説(heliocentric theory)の「heliocentric」は「太陽中心の」意味があり、直訳的には「太陽中心説」となるようです。つまり、以下のように日本語と英語では、中心となる言葉が反転しています。
英語では、地球中心説(地球が円の中心と言っているのに) 日本語では太陽が回っている。
[天動説]
英語では、太陽中心説(太陽が円の中心と言っているのに) 日本語では地球が回っている。
[地動説]
天動説を採用している以上、当時の天文学においては、地球以外の惑星の動きがどうしてもランダムウォークになってしまいました。天文図では、他の惑星は地球を中心にらせん状に回って天体運航を行っていました。そのため、英語の「planet」は、語源がギリシャ語の「planetes」(「さまよう者」や「放浪者」)を意味しており、惑星が恒星に比べて天球上をランダムに動くように見えることから付けられた名前です。
一定の位置に留まっている恒星と異なり、天球上でほぼ、惑星は他の星々の間を移動するように見えます。そのため、地球から天体を見ると、地球と同一方向に移動する「順行(prograde motion)」(西から東)、地球と反対方向に移動する「逆行(re-prograde motion)」(東から西)と言うような見た目の現象が起こります。さらに、順行と逆行が切り替わる瞬間に、惑星が一瞬止まったような「留」という現象が起きます。つまり、「順行」-「留」-「逆行」を繰り返します。そのため、見た目上は、らせん状の天体運航になります。らせん運動と言う矛盾を是正するために昔の天文図では、他の惑星は地球を中心にらせん状に回って天体運航をしているように書いてあります。
観察用の器具もない時代に、その時々の知性が未知の事柄を解明していこう懸命に取り組んだことにより後に続く色々な発見に続いてきたと思うと感慨深いです。
さて、本来なら契約書に関わる事柄を述べなければならないのですが、小さな私的展開(革命的な転回は到底できません)になってしまいました。悪しからず!
なを、以前「英文契約書翻訳時における固有名詞(人名、組織名、役職名等)について」として、契約書翻訳時・作成時(日英いずれの場合も)に気配りが必要な「組織名」と「役職名」を取り上げています。
当社では、単なる翻訳という作業ではなく、最終的に使用される文書としての完成度を重視しています。契約書・専門文書の翻訳について、用途に応じた確認が必要な場合は、こちらからお問い合わせください。当社ではお客様の作成した翻訳文を原文と対比して校正するポストエディットも承っております。
参考図書:
*「クラウディオス・プトレマイオス」(2005年8月21日 (日) 21:19 UTC)ウィキペディア日本語版。URL: https://ja.wikipedia.org