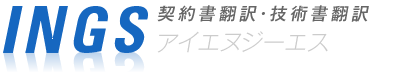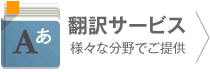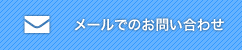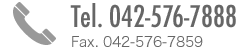前回は、英単語「on」と「off」は、それらが持ついくつかの意味について1. 「on」の本来の意味、2. 「of」の本来の意味、3. 身近な例 4. 同じ単語で「on」「off」が使われている表現について見てみました。詳しくは契約書の単語・用語 身近な英単語 ONとOFFについて(その1)に記載があります。
今回も契約書翻訳の実務経験を前提に、英文契約書の内容確認・リスクチェックの観点から解説します。前回も申し上げましたが、契約書や法務文書、技術書とは関係がないように見えますが、知っておいて損はありません。必ず知識は生きてきます。
5. cutとの組み合わせ
a. cut on:
「cut on」は文脈によって「切り傷」や「~を減らす」という意味を持つ「cut down on」など、いくつかの意味があります。
「cut on」の一般的な意味
切り傷: 「切り口」や「切り傷」という意味で使われます。
「~に切り傷がある」の意味
I got a cut on my leg. (足に傷を負った。)
He received a cut on his hand while trimming leaves. (木を選定している際に、手に切り傷を負った。)
b. cut off
「cut off」は、(…を)切り払う、(…を)断つ、やめる、(…を)切り離す、分離する、~を遮断するなどの意味があります。
The water supply was cut off.(水が止められた。)
6. takeとの組み合わせ
a. take on
「take on」の一般的な意味(仕事・責任などを)引き受ける(承諾する)、(人を)雇う、(争い・競技などで)相手する、持つようになる、帯びる、呈する、乗せる
率直に言ってあまりなじみのないフレーズですが、いろいろな意味に使われます。
the case that the lawyer has accepted to take on. (弁護士が引き受けることを承諾した事件;弁護士が受任した事件)
The Contractor shall not accept to take on the duties not provided for in this Article. (請負人は、本条に規定されていない義務の受任を承諾しないものとする。)
When a patent attorney corporation that has only one member is requested to take on a case, that member is deemed to have been designated.(社員が一人の弁理士法人が、事件の依頼を受けたときは、その社員を指定したものとみなす。)(弁理士法)
b. take off
「take off」は、ちょっと調べただけでも「脱ぐ、はずす、取りはずす、取り除く、割り引く」などフレーズとして使われるほか、名詞として、すでに日本語としても使われている「(飛行機などの)離陸」などの意味があります。
The plane took off from A runway.(飛行機はA滑走路から離陸した。)
Take off your shoes before entering this locker room with shower room.(~に入る)
Take off old grease on the shaft of motor before cleaning the motor (~を取り除く)
なを、上記の文章は、Removeを使う方がどちらかというと自然な文章になります。
Remove old grease from the motor shaft before cleaning the motor.または
Remove old grease from the motor shaft prior to cleaning the motor.
その他take offはここでは取り上げませんが様々な意味に使われます。
7. setとの組み合わせ
a. set off
「set off」は、フレーズとして出発する、(ロケットなどを)発射する、(機械などを)始動させる、相殺する等の意味があります。
この中で契約書やビジネス文書で多く使用されるのは「set off against」=〜を(別のものと)相殺する(名詞ではset off=相殺)です。
The Contractor may set off any losses arising from works not expressly provided for in this Agreement against any profits derived from the performance of the duties hereunder.
一番簡単例文ですが、この場合、この文だけですと「set off」されるのが会計上の相殺か、債権・債務上の相殺を問われることもあるので注意が必要です。
上記の例文でも特に問題はないと思いますが、「より明確化する内容」にしたい場合、以下のようにすることもできます。
The Contractor shall be entitled to set off any and all losses incurred in connection with works not expressly specified in this Agreement against any and all profits earned by the Contractor in the performance of the duties hereunder.
この中でも特に「not expressly specified」の部分は、黙示的包含を排除する場合に使われます。相殺についての記載方法は例えば、「より明確にする内容」、「一方的・自動的に相殺できる内容」などその他様々な記載方法があります。
「set off」について見たので「set on」について見てみすが、こちらは主な意味は、「~を攻撃する、襲う」となりますので割愛します。
当社では、契約書・企業法務文書を中心に、日本語から英語、英語から日本語の双方に対応し、AI翻訳を下訳として使用した文書についても、原文の意図・文脈・実務上の使われ方を踏まえた内容確認と最終仕上げを行っています。「この英文(和文)、そのまま使ってよいか判断してほしい」という場合は、こちらからお気軽にお問い合わせください。
参考図書:研究社新英和辞典(研究社)
ランダムハウス英和辞典(小学館)
カレッジライトハウス和英辞典(研究社)
日本法令外国語訳データベースシステム