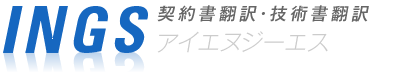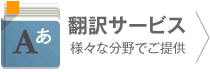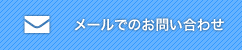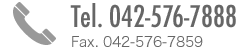今回は、英文契約書翻訳に携わる中で、経験上、よく目にしたり、よく使われる条項について契約書翻訳の観点から簡単な例文を作成してその用例(一部ですが)を見てみます。
1. 英文契約書に共通してみられる条項
前回、「契約の目的・種類のごく簡単な説明」にあるように、英文契約書には、様々な種類があります。これらの契約は、契約の種類・内容は違うものの、共通してみられる条項(契約の種類にかかわらず、同じ内容を規定している)があります。例えばよく知られているものに、「契約に適用される法律を規定する準拠法条項または適用法条項「(Governing Law)または(Applicable Law)」、「契約に関する解釈の相違、紛争の解決についての方法を定めた、管轄裁判所の合意に関する条項(Jurisdiction)、仲裁に関する条項(Arbitration)」等があります。
2. 「機密保持義務」に関する条項とは
英文契約書には、上記以外にも様々な共通してみられる条項がありますが、それらの中でも重要なものの1つとして、「機密保持義務」または「秘密保持義務」に関する条項(Confidentiality)があります。これら機密保持義務に関する条項は、「契約の当事者が契約を履行する過程で知り得た相手方の情報に関する機密保持義務を負担すること」を定めています。
例えば、「Neither party shall disclose the information obtained from the other party during the performance of the Services to any third party without prior written consent of the other party.」(例文A)簡単な例文ですが、最低限このようなことが記載されます。なお、当然のことながら書き方は、契約により多様です。
機密保持義務については、契約の種類・内容により、相手方に対する機密保持義務の負担の程度が、双方とも公平に負担するもの、または負担の程度がいずれの当事者に偏っているもの等、様々です。
機密保持義務の対象となる具体的内容は、機密保持がなされることで、財産的価値が維持できるもの、例えば、技術情報、ノウハウ、企業秘密等の他、契約により様々なものを対象とします(例えば、まれに契約の存在自体を秘匿する旨が記載されているような場合もあります)。
ただし、例えば以下に作成した例のように、技術情報、ノウハウ、企業秘密等に関しては、契約を締結する時点ですでに一般的に知られているもの、または契約の途中で当事者の過失によらず一般的に知られるようになったもの、機密保持義務に違反することなく取得したもの等は除外されるのが普通です。
例文B: The Confidential Information does not include the information that:
(i) is already generally known to the public at the time of disclosure;
(ii) becomes, at a later date, generally known to the public without a fault of the Party XXX; or
(iii) is acquired by Party XXX without violation of the confidentiality.
*これらの他にも様々なケースが規定されます。
そのほか、契約が終了した後、契約が契約期間内に中途で解除された場合でも、一定の期間、内容を指定して、機密保持義務が存続する旨の記載もあります。
例文C: Each party shall hold the other party’s Confidential Information in confidence for a period of three (3) years from the date of expiration or termination of this Agreement. (この例では3年間)
これら以外にも、様々な内容が記載されます。これらについては、機会があれば、特色のある条項をまとめてみたいと思います。
契約条項としての「機密保持義務」(Confidentiality)とは別に、「機密保持義務」そのものを「機密保持契約」または「秘密保持契約」(Confidentiality Agreement)として、1つの独立した契約とする場合もあります。名称が異なりますが、非開示契約(Nondisclosure Agreement: NDA)もこの類です。Nondisclosure Agreementを「機密保持契約」または「秘密保持契約」を称する場合もあります。一般的には「NDA」の名称で知られています。)便宜上、ここでは、「機密保持契約」とします。
3.. 「Receiving Party」と「Disclosing Party」
「機密保持義務」を1つの独立した契約にした「機密保持契約」が作成される経緯は、様々ですが、契約の当事者の呼称について、情報を開示する側を「Disclosing Party」、「Disclosing Person」または「Discloser」等と呼称し、情報を受け取る側を「Receiving Party」、「Receiving Person」または「Recipient」等と呼称する場合があります。Disclosing Party(開示当事者)、Disclosing Person、Discloser (いずれも、開示人もしくは開示者)、Receiving Party(受領当事者)、Receiving Person、Recipient(いずれも、受領人もしくは受領者)というよう呼称します。
なお、これらの表記は、「機密保持契約」ではない契約の「機密保持契約条項」または「機密保持」に関連する記述内容に使用される場合もあります。
「それぞれの当事者の名称/呼称」を用いても、何の問題もありませんが、「Disclosing Party」と「Receiving Party」としたほうが、その立場が明瞭で分かりやすく、間違いを生じることが少ないということかもしれません。特に、いずれの当事者においても、相手方に対する機密保持義務の負担の程度が公平な場合は、「情報を出した者」と「情報を受け取った者」とするほうが、分かりやすいはずです。
上記の例文Bを基にして、例文を作ってみます。
The Confidential Information does not include the information that:
(i) is already known to the Receiving Party at the time of disclosure;
(ii) becomes, at a later date, known to the Receiving Party without a fault of the Receiving Party; or
(iii) is acquired by Receiving Party without violation of the confidentiality.
双方で情報をやり取りする場合、例えばAからBへ、BからAへというような情報の流れを気にせずに、「情報を開示した者」と「情報を受領した者」を区別することができます。特に、「情報を開示した者」と「情報を受領した者」に関して、当事者に加え、各当事者の関係者、役員、従業員、下請業者、子会社等を含める場合、これらを集合的に「開示当事者」、「受領当事者」として規定すると分かりやすくなります。
参考図書:
英和大辞典(研究社)、コンパクト六法(岩波書店)、Trend(小学館)、Oxford Dictionary of English