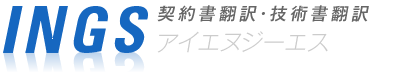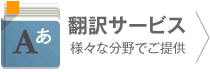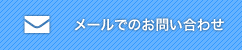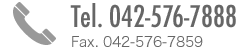英文契約書の翻訳を行っていると、「Interest」という単語を目にすることが良くあります。この単語「Interest」は、その前後の文章・内容によって、訳語が変わってくるので厄介です。その理由の1つは、(私見ですが)その昔、誰かが、単語「Interest」がある文章の翻訳を最初行った時に、それぞれの分野ごとに「Interest」という単語に対する訳語を設けたからであると推察されます。
そのためか(?)、「Interest」という単語を日本語に訳す場合に、各分野で微妙に違う訳となっています。
そこで、この単語の意味をあらためて確認し、まとめてみることにしました。先ずは、英々辞典を参照してみます。
英々辞典The New Oxford Dictionary of Englishでは、「Interest」を以下の様に定義しています。
- Mass noun The state of wanting to know or learn about something or someone.
She looked about her with interest. - Mass noun money paid regularly at a particularly rate for the use of money lent, or for delaying the repayment of a debt.
the monthly rate of interests. - The advantage of benefit of a person or group.
the merger is not contrary to the public interest
興味、関心、興味を起こさせるもの、関心事、趣味、興味をそそる力、面白さ、興趣、重要(性)、重大(性)
上記の意味だけでなく,利益、利害関係があり、利害関係が発生する状況では「利益,利子」などの意にも使用されています。
また、利子(郵貯)(銀行の場合は、利息)と言う意味がありますが、利子とは、貸借した金銭などに対して、ある一定利率で支払われる対価。貸し借りの言う利害関係から生じた得が利子、利息に転用されたようです。

どうも、単語「Interest」を翻訳する際に、ある特定の分野において、その分野の対応する日本語に置き換えた際に日本語の実情に合わせて色々な訳を当てはめた(始めに日本語ありきの)可能性があるかもしれません(これは、あくまでも私見です。学問的なエビデンスがあるわけではありません。なを、いつものことですが、「単語の意味、用法」については、辞書や専門書をご覧ください。)
「Interest」を訳す場合は、状況もしくは一緒に使われている単語でどの訳にするか(どの日本語を使うか)を決めましょう。
参考までに、いくつかの分野で例文を作成してみました。
The terms and conditions of the loan, loan period and interest rate, etc. will be determined after further discussions between A and B.
借入れ条件、その期間、利率等については、別途協議の上定めるものとします。
Positions of outside directors held at other companies are disclosed, but those at publicinterest corporations are not.
社外取締役の兼任状況は開示されても、公益法人との兼任は開示されていない。
In order to avoid interestrate fluctuation risk associated with some of the securities, loans payable and bonds, this Company applies hedge accounting using various derivatives instruments such as interestrate swaps and currency swaps.
当社は、一部の有価証券、借入金及び発行社債等に関連する金利変動リスクを回避するため、金利スワップ及び通貨スワップ等のデリバティブ取引を用いてヘッジを行っています。
Long-term borrowings at floating rates are subject to special treatment as interest rate swaps, with the related interest swap, and the value is calculated as the present value,
金利スワップと共に、変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、また、その数値は現在の数値として算定されます。
Some natural sample types vary a lot, both in origin and composition, leading to highly on-linear relationships between the parameter of interest and the spectra.
一部の天然のサンプルのタイプは由来や成分により大きなばらつきがあるため、対象パラメータとスペクトルが非線形な関係を導く可能性が高くなります。
We would like to provide you with products and services we think may be of interest to customers.
私たちは、お客様にご興味をお持ちいただけるような商品及びサービスを提供してまいります。
A survey will be taken to determine their current interest in the committee’s activities and opinion regarding merger.
委員会の活動への現在の利害と合併に関する意見についての調査を行います。