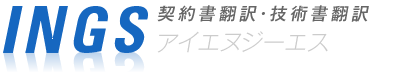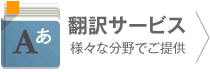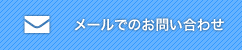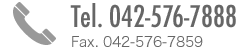英文契約書において経験上、よく目にしたり、よく使われたり、または知っておいて損はないと思われる単語と用語について、契約書翻訳の観点から簡単な例文を作成してその用例(一部ですが)を見てみます。今回は、主に「disability」と「discharge」について、簡単な例文を作成してその用例(一部ですが)を見てみます。
1.「disability」について
意味としては、「無能、無力、(法律上の)行為無能力、障害」等、ネガティブな感じの単語です。
英文契約書の中での用いられ方に関しては、例えば、以下に作成した例文のように、契約の解除要件の1つとしてあげられる場合などがあります。
No disability, restriction or prohibition affecting its ability to execute this Agreement shall exist.
(本契約を履行する能力に影響を及ぼす障害、制限または禁止は存在しない)
ただし、個人的な印象としては(あくまでも個人的な)、通常の契約書よりも、むしろ就業規則とか労務契約あるいは保険関連の契約、その他委任状等、様々な翻訳に際して登場する単語です。以下に作成した例文で見てみます。
“Disability” shall mean a condition that renders an individual unable to engage in substantial gainful activity by reason of any medically determinable physical or mental impairment.
(「障害」とは、医学的に診断可能な身体的もしくは精神的欠陥事由により、実質的な報酬を受ける業務に従事することが不可能である状態を意味する。)
This power of attorney shall be exercisable notwithstanding his or her subsequent disability or incapacity.
(この委任状は、その後の障害または無能力にかかわらず、行使可能です。)
そのほか、以下のような例もあります。
With respect to any person who constantly lacks the capacity to discern right and wrong due to mental disability,(精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、)(民法)
2.「discharge」について
名詞としての「discharge」は、通常「排出」、「放電」、「荷卸し」、「解雇」等の意味で用いられる場合が多いようです。
例えば、This plant discharges industrial waste into a river in violation of the laws.(この工場は、法律に違反して産業廃棄物を河川に排出しています。)
英文契約書の例文を1つ作成してみました。
Even a person who is discharged by a violation of this Agreement may seek relief based on the laws and regulation of Japan.
(本契約に違反して解雇された者でも、日本の法令に基づき救済を求めることができます。)
ただし、「discharge」には、「(義務の)履行」、「免責」等の意味でも用いられます。そのため「discharge」を「排出」、「放電」、「荷卸し」、「解雇」等の意味(何かを外に出すような感じで)のみで捉えていると和文英訳の場合、誤訳を生じる可能性もあります。ここでは、「(義務の)履行」の意味で使用されているdischargeの例文を作成してみました。
The Contractor shall perform and discharge its duties under this Agreement.
(契約者は、本契約に基づきその義務を遂行し、履行するものとします。)
The termination of this Agreement shall not discharge either of the parties from its obligations nor shall it discharge the responsibility of a party who violates the terms and conditions hereunder.
(本契約の終了は、いずれの当事者からもその義務を免除するものではなく、また本規約に違反する当事者の責任を免除するものでもありません。)
なを、この場合、「discharge」の代わりに「exempt」を使用し、「exempt from person xxxx」 というような形式を用いて書き換えることもできます。むしろ「exempt」を使用するほうが一般的かと思われます。この用例については、「exempt」、「exemption」を取り上げる際に改めて見てみたいと思います。
そのほか「discharge」は他の語と組み合わせて、以下のような用語を作ります。
discharge of duties(義務の履行)、discharge of the obligation (債務の弁済)
参考図書:
- 法律用語辞典(有斐閣)
- 英和大辞典(研究社)
- コンパクト六法(岩波書店)
- Trend (小学館)
- Oxford Dictionary of English
- 日本法令外国語訳データベースシステム他