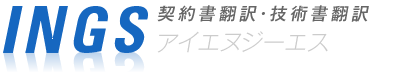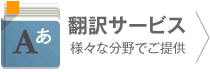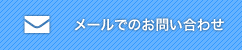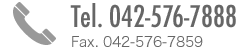今回は、英文契約書で使用されるemployee、employer、enact、encroach、encroachment、encumbrance、endorse、endorser、enforceについて作成した例文その他を通して契約書翻訳の視点から英文契約書での使われ方の一例を作成した例文その他を通して見てみます。
| employee | 従業員、被用者、労務者 |
| employer | 使用者、雇用主 |
EmployeeとEmployerは、誰でも知っている言葉で、特に取り上げる必要もなかったのですが、良く使われるので例文を作ってみました。
Subcontractor is, and shall at all times be, an independent contractor with respect to all services rendered under this Agreement, and shall not be deemed an employee or agent of the parties. (下請業者は、常に、本契約にもとづき提供されるすべてのサービスについて、独立業務請負人であり、独立業務請負人であるものとし、本契約の当事者の従業員または代理人とみなされない。)
The parties hereto acknowledges that there is no employer/employee, principal/agent, joint venture, partnership relation or any other similar agreement between the parties. (本契約の両当事者は、両当事者間に、雇用者/被雇用者、親会社/代理人、ジョイントベンチャー、提携の関係またはその他の同様な契約が存在しないことを承認する。)
| enact | (法律を)制定する、規定する |
It is enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America.(米国上院と下院において制定される。)
Reference in this Agreement to any statute or statutory provision includes a reference to that statute or statutory provision as from time to time amended extended or re-enacted. (制定法もしくは制定法の条項に対する本契約における言及は、随時、変更、拡張または再制定される制定法もしくは制定法の条項に対する言及を含む。)
| encroach | 侵入する、侵害する |
| encroachment | 境界侵奪,不法侵奪 |
If the Lessor finds that the Lessee has encroached beyond the boundaries of the leased land, the Lessee must, upon notice by the Lessor and at its own expense, immediately or within the time specified by the Lessor rectify and remove the encroachment to the Lessor’s satisfaction. (賃借人が、借地の境界を侵害していることを賃貸人が発見した場合、賃借人は、賃貸人からの通知を受け次第、自らの費用で、直ちにまたは賃貸人の指定する期限内に、当該不法侵奪状態を賃貸人の満足するように是正し、解消しなければならない。)
| encumbrance(incumbrance) | (財産上の)負担(債務・抵当権など)、土地負担、土地、船舶上の担保 |
言葉の意味としては、仏語のじゃま物(者)、やっかい物(者)などからきているそうです。辞書を見ると、法律的な意味の場合、不動産に付帯する負担、債務、制限(抵当権等)と言うニュアンスで使われていることをよく見かけますが、不動産にかかわらず、財産上の負担、抵当権・債務として使用されるケースもそれなりに見受けられます。
The parties hereto shall not create, incur or permit any encumbrance, lien, security interest, mortgage, pledge, assignment or other hypothecation upon this Agreement or any right granted herein. (本契約の当事者は、本契約または本契約で付与された権利に基づき、いかなる債務、抵当権、動産担保権、担保、質権、譲渡、または、その他の担保契約を作成せず、負担せず、または、許可しないものとする。)
When the object damaged by flood belongs to the offender, the provision of the preceding paragraph shall apply only when the object is subject to attachment, encumbrance, lease or insurance.(浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。)(刑法)
| endorse | 保証する、承認する(事実であると認める)、裏書する、 |
| endorser | 裏書人、譲渡人(transferor)、身元保証人 |
The seller shall endorse or warrant the merchantability and/or fitness for use and/or safety of the Products.(売主は、製品の商品性および/または使用のための適合性および/または安全性を事実であると認め、または保証する)
(iii) In cases of the spouse of a Japanese national, a letter of endorsement by the Japanese national residing in Japan; in cases of the specially adopted child or child of a Japanese national, a letter of endorsement by the Japanese national residing in Japan or other endorser residing in Japan.(三 日本人の配偶者である場合には、本邦に居住する当該日本人の身元保証書、日本人の特別養子又は子である場合には、本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書)(出入国管理及び難民認定法施行規則 別表)
| enforce | 実施する、施行する、強いる、強要する、強める、強調する、強く主張する |
Each party has the right to enforce this Agreement against the other party by temporary restraining order, injunction, or other equitable relief, without proving actual damages.(各当事者は、実際の損害賠償を証明することなく、保全命令、差し止め、またはその他の衡平法上の救済により、相手方に対して本契約を執行する(契約を行わせる)権利を有する。)なを、enforceは、「(人に)に~させる」の意味よりも、以下のように「施行する」、「実施する」の意味で使用される場合が多く見受けられます。
The prefecture concerned shall pay the necessary expenses for the Prefectural Governor to enforce this Act. (都道府県知事がこの法律を施行するために必要とする経費は、当該都道府県の負担とする。) (建設業法)
No person other than a party to this Agreement shall have any rights to enforce any term of this Agreement. (本契約の当事者以外の者は、本契約の条件を実施するためのいかなる権利も有しない。)
いずれも英文契約書になくてはならない単語と使い方のいくつかの例をとりあげてみました。
参考図書
ランダムハウス英和大辞典(小学館)
研究社新英和辞典(研究社)他
法律英単語(自由国民社)
日本法令外国語訳データベースシステム