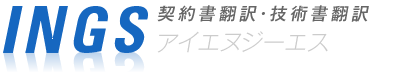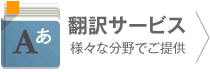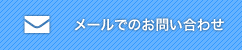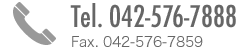英文契約書の慣用表現 (without prejudice to ~、calendar days、business days、business hours)
英文契約書で使われる慣用句的な用語 ― いわゆる、リーガルジャーゴン(Legal Jargon)の中で、前回は「null and void」、「assign and transfer」などを取り上げました。今回は、「without prejudice to ~」「calendar days」、「business days」, 「business hours」について見てみます。契約書翻訳の視点から概説します。
1. 「without prejudice to ~」(…を侵害せずに、そこなわずに、…の不利益とならないように、…影響を与えることなく)
かつての辞書を見ると、「…を毀損することなく」と難しい漢字で意味が記載され、たしか、改正前の民法でも、最近までこの漢字を使用していたような記憶があります。その名残か、今でも「毀損」という漢字を使う場合をたまに見かけます。
いずれにしても、英文契約書の慣用表現の1つです。この条項が置かれる理由の1つは、例えば、相手方に契約違反があり、その相手方に損害賠償を求めることができることが契約上規定されている場合、その契約が解除されても、損害賠償を求めることができる権利は引き続き有効であり、また、損害賠償以外の他の救済手段にも契約解除は影響しないというあたりでしょうか。(1つには、ある理由で契約を解除する場合、「当該契約解除により、契約締結以前(元の)の状態に戻り、損害賠償請求権は、消滅する」という英国法の考え方を排除するためと言われます。)
上記以外の場面でも、単に、例えば、「Without prejudice to any other provision of this Agreement,」(本契約の他の条項に影響を与えることなく、)などと用いられることがあります。
ここでは、「契約解除の条項」で用いられる場合の例として、
「Either party may, without prejudice to any other rights or remedies hereunder terminate this Agreement if…」(いずれの当事者も、本契約に基づく他の権利または救済策に影響を与えることなく、…の場合、本契約を解除することができる)。
見ての通り、この一文があることで、例えば、相手方の重大な契約違反による契約解除の場合でも、救済手段や損害賠償請求権を含む契約上の権利は引き続き有効とされます。
その他、「without prejudice to ~」を使用しない表現もありますが、ここでは述べません。「契約解除の条項」については、ブログ「英文契約書の条項」の内「一般条項」で、先々取り上げてみたいとおもいます。
2. 「calendar days」(暦日)、「business days」(営業日)「business hours」(営業時間)
「calendar days」(暦日)は、読んで字のごとく暦の日、「business days」(営業日)は、一般には、銀行や企業の営業日です。いうまでもなく、契約における日付は、重要な意味を持ちます。
これらが定義条項で定義される場合もあります。例えば、
「Business Day means any day other than a Saturday and a Sunday on which banks are open for business in Japan」(「営業日」とは、日本国において、土曜日と日曜日を除き、銀行が営業のために開店する日を意味する。)
「Business Hours means 9:00am to 5:00pm JST on a Business Day.」
(「営業時間」とは、営業日における日本標準時の9:00amから 5:00pmまでを意味する。)
以前触れた「Notice」(通知)条項では、
「Notice shall be deemed to have received five (5) business days after mailing.」(通知は、郵送後、5営業日で送達されたとみなされる)。
「Unless otherwise specified in this Agreement, the notice periods shall be calculated in calendar days.」(本契約で特段の記載がある場合を除き、本通知期間は、歴日で計算されるものとする。)
上記の契約解除でも、その通知に関して「Party A may terminate this Agreement upon five (5) business days’ notice to Party B;…」(Aは、…に関して、Bに対する5営業日の通知により本契約を解除することができる)
支払いについて、例えば、
「The payment is due net immediately after receipt of the invoice.」(支払いは、請求書の受領後、直ちに支払うべき正価を支払う。)
「Party A will pay an up-front amount of USD xxx to Party B within 14 days upon the signature of this Agreement.」(Aは、本契約書調印後14日以内にBに対し前払い金として米国ドルxxxを支払う。)
その他、支払、支払期日、サービス・物品の提供と受領、情報の提供・公開、訴訟、法的措置に関するもの、などなど、当然のことですが、日付や時間の規定は、多くの場面で用いられます。
参考図書:ビジネス法律英語辞典(日経文庫)
ランダムハウス英和大辞典(小学館)他